| 3.シェルナース効果調査事例 |
|
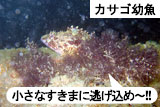 
|
|
|
|
| Copyright (C) 2001-2005 Ocean Construction Co.,Ltd. All Rights Reserved. |
| 3.シェルナース効果調査事例 |
|
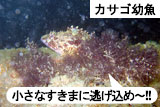 
|
|
|
|
| Copyright (C) 2001-2005 Ocean Construction Co.,Ltd. All Rights Reserved. |